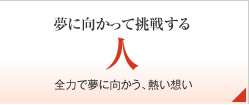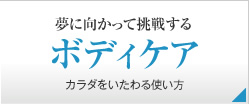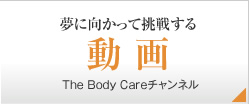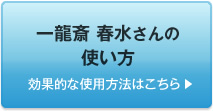1952年北海道生まれ。声優学校在学中から、数々の大ヒットアニメに出演。現在も、映画の吹き替えやナレーターとしても活躍中。1992年に講談師の一龍斎貞水に入門し、春水の号を受ける。1996年に二ツ目に、2004年真打ちに昇進。
一龍斎 春水さんのストーリーインタビュー
小さい頃、テレビでアニメを見て、絵に声を入れることで命が宿ることに感動したんです。わたしは、小学生の頃から、朗読することや校内放送で声を届けることが大好きだったんですよ。だから、私も自分の声でキャラクターを動かしてみたいと思って、声優の世界に飛び込んだんです。
声優になってからの毎日は、先輩方に支えられ、素敵なキャラクターとも出会って、本当に幸せでした。でも、だんだん仕事が進むにつれて、より高い演技力を求められるようになったんですね。それで、お芝居の勉強がしたいなと思って劇団に入ったんです。さらに、声での芝居をスキルアップするために、台本や小説をドラマチックに読み上げる活動もしていました。でも、そうやってお芝居をしていくうちに、お客様がお行儀良く聴いているのではなく、もっとリラックスした中で聴いていただけるものはないかなって思うようになったんです。その時に、今の師匠である一龍斎貞水という人に出会ったんです。たった1人、高座の上に座って、お客様を自由に動かす。お客様が物語の中に入り込んで、自然と前にのめり込んだり、笑ったり泣いたりしているんですよね。すごい話芸だと思ったんですよ。「講談に出会うために、これまでの人生があったかもしれない」と思うほどに感激したんです。
講談に入門したのは、40歳の時です。見習いからのスタートで、師匠や先輩の履物をそろえたり、着物をたたんだり、お茶を入れたりすることからはじまりました。伝統話芸の世界ですから、上下関係もきっちりしていますし、ゼロからひとつひとつやっていかないと上には上がれないんですよ。それまでは、スタジオに行けば誰かがお茶を入れてくれるような毎日でしたので、180度生活が変化しましたね。でもそうやって、見習いとして経験を積む中で、講談の話に出てくるいろんな立場の、いろんな仕事をする人の想いがわかるようになってくるんです。講談は「人間を語る」もの。人の行動や言葉の裏にある想いを学ぶことは、とても重要なんですよね。
わたしの師匠は、1つ1つお稽古をつけたりするよりも、「自分で見て、技を盗んでいけ」っていうタイプなんです。だから、自分でやりたい話を見つけてきて、自分で内容を組み立てて、とにかくお客様の前でやってみないといけないんですよ。そのなかで、お客様が飽きているなとか、のってきてくれているなという感覚をつかんで、その場で内容を調整しながら話していく。1つのお話をお客様と一緒につくりあげていくんですよ。この一体感が講談の魅力ですし、それに触れる度、この世界に入ってよかったなと思います。

見習いからのスタート、自分から動いて学ぶ毎日